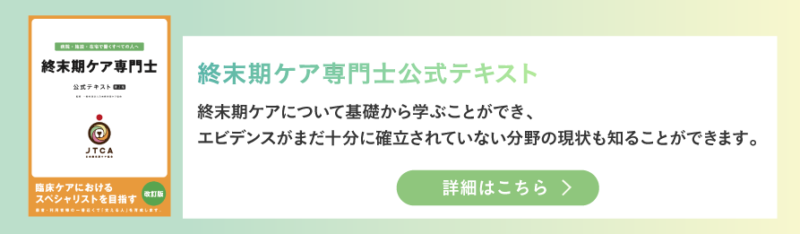死生学と看護

- 目次
死生学とは
死生学とは「死や命に関連したテーマを扱うことで、生きるとは何かを考える学問」です。
「生き死に」に良し悪しはありません。
死と向き合うことは、 どう生きるかを問う、ということです。
死別・悲嘆・尊厳死・臨死体験・終末がん患者へのケア・死生観・死後の世界・自殺・孤独死・命の教育・震災・トラウマ・脳死・・・・など。
こうして挙げていくと、死と命に関連するさまざまなテーマが存在するのが分かります。
死生学の目的は「死に関連したテーマから、生きるとは何かを考えること」であり、 死のみに焦点を当てた学問ではないことを心得ておきましょう。
臨床における死生観
死生観を考えるうえで看護師や医療従事者に求められることは、さまざまな場面において、自分自身の死生観を振り返り、思考を重ね、広げていき、患者さんそれぞれの思いに臨機応変に対応していく姿勢です。
姿勢(スタンス)
目の前の人ありき
目の前にいる人の思いを、何とかかたちにしていくことに重きを置く。
伴走
意思決定など重要な場面で、何かを選択することは、迷いや不安など、大きな苦悩を伴います。
しかし、あくまでも生き死にを背負っている患者さん本人が、その人生の主人公です。
患者さんの思いを置き去りに医療者が先行することなく、その人の抱える戸惑いに配慮しながら伴走することが重要です。
全肯定
人生の主人公である患者さんは、いかなる状況においても否定されようのない存在であり、他の誰もその人の「生き死に」に、良し悪しをつけることはできません。
ありのままの患者さんを受け入れる姿勢が大切です。
自己理解
なぜその現場に関わり続けるのかを自問自答し、医療者の思う望ましい方向性を押し付けないことが大切です。
自己の傾向はどうか、理解しておきましょう。
関係性
医療者と患者さんとの関係は、支える・支えられるという一方的なものではなく、医療従事者も患者さんから多くを学びエネルギーをもらう相関関係にあります。
また、普遍の死を持つ同じ存在であることに変わりはないのです。
これらを踏まえ、専門性を活かしながら、終末期にある人が「その人らしい自分」であり続けられるように関わることが大切です。
医療者は、「生き死に」の主人公である患者さんの思いを、何とか形にしていくプロセスの中で、さまざまな学びを得ます。
特に終末期では、患者さんこそが生きることを見つめる「先生」であると言えるでしょう。
QOD(Quality of Death/Dying)
皆さんはQODという言葉を知っていますか?
死という自然の摂理は変えられません。
でも心の持ちようで、どのように最期までを過ごすのかは違ってきます。
死が間近に迫った場合には、「その人らしく生活できているか」という「QOL」よりも、どのように死を迎えるかに焦点を当てた「QOD」という考え方が注目されています。
これは死の一時点ではなく、亡くなるまでの過程や遺族ケアも含みます。
そして、いかにその人らしく死を迎えるか、という終末期の質を表しています。
遺言を残す、人生を振り返る、また家族や仲間とコミュニケーションをとることなどでQODの質が高まるといわれています。
終末期の患者さんは、死の過程で経験する苦痛、不安、大切な人との別れに対する寂しさや悲しみ、死に対する恐怖など複雑に絡み合う感情を受け止めています。
その人らしい最期を迎えるために、多角的な視点で寄り添い、QODを意識した関わりがとても大切になります。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。