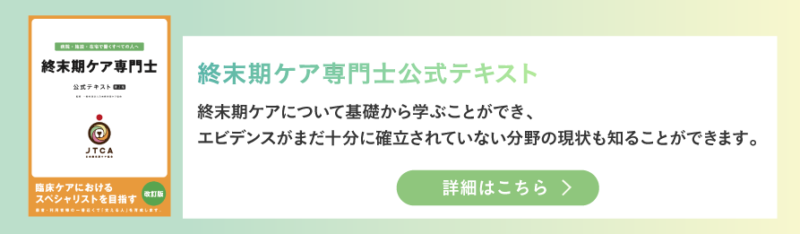ターミナルケア(終末期医療)

- 目次
ターミナルケア(終末期医療)とは
ターミナルケア(終末期医療)とは余命が残りわずかになった方に対し、残りの人生を穏やかに過ごせるように。サポートすることをいいます。延命を目的とした治療を中止し、身体的・精神的苦痛を緩和や除去をして生活の質(QOL)の維持・向上を目的としています。ターミナルケアは病院だけでななく、介護施設や自宅などでもおこないます。患者さんがその人らしく生き抜くために患者さんが望む場所でターミナルケアをおこなうことが望ましいとされています。患者さんが自分の意思を主張できないようになっても適切なターミナルケアを実施できるように、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」というものを厚生労働省は策定しています。
終末期の定義
- 複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること
- 患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること
- 患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること
(公益社団法人 全日本病院協会 「終末期医療に関するガイドライン~よりよい終末期を迎えるために~(平成28年11月)」より引用)
ターミナル期に出現する症状の特徴
ターミナル期にある人の生活状況を経過観察し原因の除去や予防策を実施していく事で、少しでも苦痛を取り除く事が大切です。その具体例を挙げていきます。
① 栄養状態ー食欲不振・水分量や食事量の低下
② 排泄―便秘・便失禁、尿量減少・尿失禁
③ 呼吸の不規則が起こり、やがて浅い呼吸に変わる
④ 体温が下がり、手足が冷たく青白くなる
⑤ 脈拍のリズムがみだれ、段々確認しづらくなる
⑥ 心機能の低下により、血圧が下降する
⑦ 呼んでも反応が小さくなり、だんだんと体の動きが減り、次第に傾眠傾向になる
⑧ 唇や爪が青紫になるチアノーゼがみられる
⑨ 精神状態―意識レベルの低下・意識混濁・せん妄・幻覚・臨死体験
倦怠感で身の置き所のなさがあり、倦怠感が緩和する時間帯に日常生活動作を行なえるといいでしょう。
マッサージや温罨法などのリラクゼーションをはかることも有効です。
不眠には睡眠薬を担当医に処方してもらうなど、出来る限りの苦痛軽減に努めていく事が大切です。
まずは、心と体のサインを「聞く」こと
ターミナル期における患者さんは症状の悪化・孤独感・迫りくる死への恐怖などから精神的ストレスを感じます。
治療では解決しにくい身体的な苦痛も出現します。
それらが要因となり、せん妄や不眠を引き起こします。
必要に応じて投薬により、負担を軽減を目指します。
薬剤投与だけではなく、環境要因に働きかけることも重要な支援です。
部屋の照明・室温調節・騒音予防等の環境整備・時計やカレンダーを見やすい場所に配置する等の配慮をする、必要な物品を手元にそろえる、マッサージや清拭なので心地よさを感じられるケアを提供する、などです。
これらの役割には、保清、マッサージ、環境整備のスキルを磨かなくてはいけません。
それらのスキルがあってこそ、自分たちの声掛けも生きてくるのです。
バイタルサインの変化について
ターミナル期のバイタルサイン(脈拍、呼吸率、体温、血圧)は通常と異なる変化が見られます。
これらの変化は、身体の機能が崩壊し、臓器の不全が進行しているために生じます。
以下に、主な変化とその理由について説明します。
1.脈拍
初めは脈拍が増加します。これは身体がストレス反応を示し、交感神経が活性化するためです。
疼痛や不安、または体内の物理的な不調に対する反応です。
しかし、ターミナル期の進行に伴い脈拍は徐々に遅くなります。
これは心臓の機能が低下し、徐々に衰えるためです。
心臓は酸素や栄養素を供給する能力を失い、脈拍が減少します。
2.体温
体温が低下することがあります。
これは代謝が減少し、エネルギーの生産が難しくなるためです。
3.呼吸
呼吸も初めは増加することがあります。
体は酸素を確保しようとし、不安や疼痛に反応します。
しかし、ターミナル期に入ると呼吸は不規則になり、浅くなることがあります。
これは、呼吸筋の衰弱や肺の機能の低下によるものです。
4.血圧
血圧は変動が見られます。
初期のターミナル期では血圧が上昇することがありますが、終末期には血圧が急激に低下することがよくあります。
これは循環機能と臓器の機能が低下するためです。
5.意識レベル
意識が低下し、徐々に傾眠状態で意識レベルが低下して昏睡状態に入ることがあります。
これは脳に酸素供給が不足するためです。
これらの変化は、ターミナル期における身体機能の衰えと臓器の機能低下に関連しています。
病気や老化が進行し治療が難しくなるため、医療的サポートやケアが重要です。
ただし、すべての人で同じ変化が見られるわけではなく個人差があります。
呼吸機能の変化について
特に呼吸器機能障害は心肺機機能に影響を及ぼしには命に関わることがあるため、十分注意する必要があります。その場合、酸素療法も必要になります。この観点から以下に異常呼吸について書き出しておきます。
1.チェーンストークス呼吸
リズム異常、無呼吸と深く早い呼吸が交互に出現
2.クスマウス呼吸
異常に深く遅い呼吸が持続
3.下顎呼吸
下顎を下方に動かし、口を開いて呼吸(亡くなる数時間以内の場合が多い)
4.鼻翼呼吸
鼻翼が呼吸に応じてピクピクする
5.陥没呼吸
胸腔内が陰圧になり呼吸時、胸壁が陥没する
6.肩呼吸
肩を上下させて呼吸する
呼吸困難時の対応としては、体位を座位や起座位(ベッドの上部を上げ、枕をあてがい固定)が有効です。しかし、長時間同一体位でいる事は褥瘡発生の原因にもなります。そのため、2~3時間毎の体位変換や電動ベッド、体位変換機能のあるエアマットなどを早期に導入していく事が必要です。
また、上記のような呼吸の変化に注意して肩呼吸や下顎呼吸になってくると、死期が迫ってきていると考えて注視していきます。
ターミナル期の身体の変化
ターミナル期の状態では、身体は色々な変化が起こります。
以下はその主な症状と経過に関する情報ですが、病状は個人差が大きく特定のがんの種類や進行度によっても異なります。
1.体重減少
癌末期の方はは食欲が低下し、体重減少がみられます。
2.倦怠感
患者は持続的な倦怠感を経験し、日常活動が難しくなります。
癌が身体のエネルギーを消耗すること原因の一つです。
3.疼痛
癌の進行に伴い、患者は疼痛を感じることがあります。
癌が周囲の組織に圧迫をかけるか、神経に影響を及ぼすことが痛みの主な原因です。
4.呼吸困難
疾患によっては呼吸困難を引き起こす可能性があります。
腫瘍が気道や肺組織を圧迫する場合もあります。
5. 浮腫(むくみ)
癌末期の患者は、浮腫が下肢や腹部にまで広がることがあります。特に下肢や腹部でよくみられます。
これはがんの進行に伴う体液の滞留が原因です。
リンパ管や血管が圧迫されたり、肝臓や腎臓の機能が低下することが浮腫に影響している可能性があります。
6.精神的な変化
癌末期には精神的な負担も高まります。患者と家族の精神的なサポートが重要です。
ターミナル期のケアの実際
ターミナル期の患者へのサポートは非常に重要です。
医療・介護チーム(医師や看護師、ケアマネージャー、介護スタッフなど)と家族の方々と相談や連携をして、患者の現状起こっていることに対して出来るだけ苦痛を減らしていく事が大切です。
1.倦怠感、疼痛の対処
患者が持続的な倦怠感がある場合や疼痛がある場合は、適切な薬物療法や痛みの緩和が出来るので、医師に相談し、早期に苦痛の緩和を図る必要があります。
2.呼吸困難の対処
吸困難がある場合、クッションなどを使用して安楽な体位を本人と相談しながら実施し、酸素療法や呼吸療法を検討することも重要です。
3.浮腫の対処
浮腫が出現している場合、リンパ浮腫の管理や体液の排出を促すため、下肢の挙上やマッサージ、関節可動域訓練、保湿、足浴などが有効な場合もあります。
4.精神的なサポート
患者と家族は精神的なサポートを受けることが大切です。
出来る限りその時の不安や心配事を傾聴して、孤独を感じることがないように心のサポートもしていく意思を伝えることで安心感や不安の軽減に努めていきます。
最後に
最も重要なのは、患者とその家族のニーズに合わせたケアを医療・介護チームと協力し、状況を見極めて適切なケアやサービスを提供していくことです。
どの職種がキャッチした本人の想いであっても、チームで共有できる関係性を作りましょう。
そのためには、チーム間でコミュニケーションにおいても礼儀と心配りを忘れないこと、指示的態度にならないこと、職種ごとの役割を明確化することが大切です。
最期が近づいてくると、意識が低下しウトウトしてる時間が長く、呼びかけても反応しなくなり傾眠状態になっていきます。
意識がなくても耳は聞こえていることを家族に説明し、手を握り、話しかけけてもいいことを伝えます。
ターミナル期のケアにおいて、もっとも大切なことは「つながり」です。
物理的・心理的・社会的に、人とのつながりが感じられるように、最期まで残したいつながりを続けられるように。
終末期ケア専門士の皆さんにはぜひそのような支援を広げてほしいと思います。
参考文献
終末期ケア専門士 公式テキスト
鈴木志津枝 内布敦子 編集,成人看護学 緩和・ターミナルケア看護論 第2版,ヌーヴェルヒロカワ,2011,380p
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。