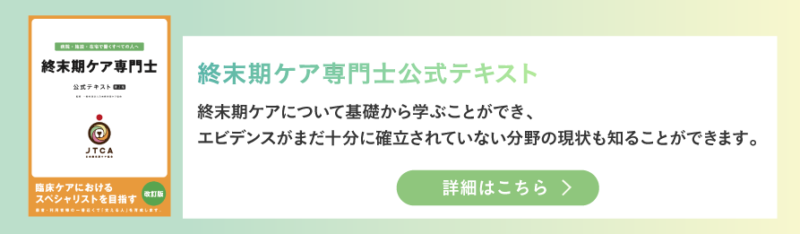ユマニチュードとは?|大切な「4つの柱」と「5つのステップ」
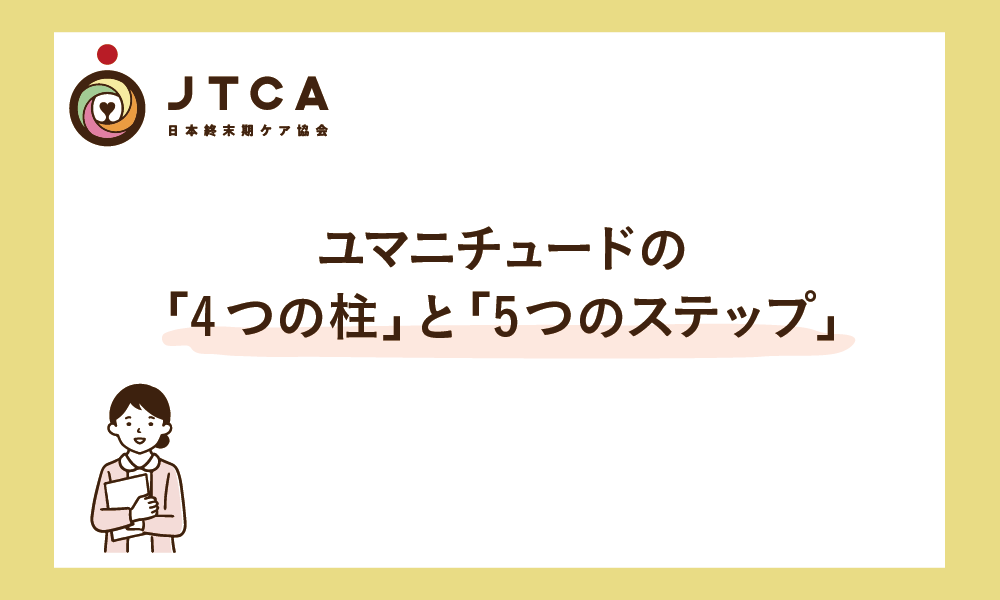
- 目次
ユマニチュードとは
ユマニチュードとは、1979年に体育学の専門である2人のフランス人、イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティが生み出したケア技法です。
ユマニチュードとは、フランス語の造語で「人間らしさを取り戻す」を意味します。
「人間としての尊厳」と「その人らしさ」を大切にし、「あなたを大切に思っています」「あなたはここにいますよ」というケアを行う人の優しい気持ちを伝える技法であるとともに、ポジティブな関係を構築するためのケアの哲学でもあります。
ケアを必要とする全ての人が対象となるケア技法ですが、今回は認知症ケアとユマニチュードについてとりあげてみました。
介護に活かすユマニチュード
ユマニチュードを実践する際の基本は、「4つの柱」と「5つのステップ」です
ユマニチュードの「4つの柱」
4つの柱は、ケアを受けている人に「あなたは私にとって大切な存在」と伝えるための技術です。
柱は1つだけではうまくいかないため、ケアをするときには柱を組み合わせて行うことが重要です。
私たちはコミュニケーションを取るとき、無意識に言語・非言語メッセージを相手に伝えています。
ケアを行う時には非言語メッセージが重要な役割を果たします。
ユマニチュードでは言語・非言語メッセージをお互いに交わし合うコミュニケーションにより、ケアを受ける人とケアする人が良い関係を築くことをケアの目的としています。
見る
・同じ目の高さでみる(平等な存在)
・近くから見る(親しい関係)
・正面から見る(相手に対して正直)
「見る」ことで『あなたを大切に思っています』というメッセージを伝えます。
「見ない」ことは、『あなたは存在していない』というメッセージになってしまいます。
話す
・低めの声で話す(安定した関係の実現)
・大きすぎない声量(穏やかな状況の実現)
・前向きな言葉を選ぶ(心地よい状態の実現)
・相手から返事がなくても無言にならない(心地よい時間の共有)
優しさを届けるためには、ケアの場に言葉をあふれさせる工夫が必要です。
無言は『あなたは存在していない』という否定的なメッセージになってしまいます。
触れる
・広い面積で触れる
・掴まない
・ゆっくりと手を動かす
・背中や肩などから触れ、手や顔など敏感な場所にいきなり触れない
掴む行為は自由を奪うことを意味し、認知症行動心理症状(妄想・徘徊・ケアへの抵抗など)のきっかけになります。
※「見る」「話す」「触れる」は、できるだけ同時に行うのがよいです。
立つ
・骨粗しょう症の予防
・筋力維持
・循環状態の改善
・肺の容積を増やす
ユマニチュードでは、「一日20分立つ時間を作れば、寝たきりにならずに立つ機能を維持できる」としています。
ユマニチュードの「5つのステップ」
ユマニチュードではすべてのケアを「5つのステップ」で実施します。
| ステップⅠ | 出会いの準備 |
| ステップⅡ | ケアの準備 |
| ステップⅢ | 知覚の連結 |
| ステップⅣ | 感情の固定 |
| ステップⅤ | 再会の約束 |
ステップⅠ:出会いの準備…自分の来訪を知らせる
・3回ノックする
・3秒待つ
・返事があれば1回ノックして入る
・ベッドボードをノックする
認知症の人は判断や理解に時間がかかることがあるため、待つことが大切です。
ステップⅡ:ケアの準備…ケアの合意を得る
・まず「会えてうれしい」気持ちを伝えます。いきなりケアの話はしない
・「見る」「話す」「触れる」を使い20秒から3分程度でケアの合意を得ます
・合意が得られなければケアは行いません。諦めることも技術です
良い関係を築くために、相手が嫌がることは行いません。
ステップⅢ:知覚の連結…合意が得られたらケアの実施
・ケア中は、常に「見る」「話す」「触れる」のうち2つを行います
・五感から得られる情報は常に同じ意味を伝えること
・ケア提供者が行っている動作を言葉にしながら行う
少なくとも二つ以上の感覚へ、調和的でポジティブな情報を伝え続けることが大切です。
ステップⅣ:感情の固定…共に良い時間を過ごしたことを一緒に振り返る
・「気持ち良かったですね」
・「協力してくださいましたね」
・「お話しできて楽しかったです」などを伝える
ポジティブな「感情記憶」を残す。
ステップⅤ:再会の約束…約束をすることで次のケアを行いやすくします
・「また明日、12時にきますね」など具体的に伝えます
覚えてもらえるようにカレンダーなどに書き込むと良いです。
認知症ケアに対するユマニチュードの効果
認知症ケアにユマニチュードを活用することで、ケアを受ける人・行う人の双方に以下の効果が期待できます。
ケアを受ける人
・精神状態が落ち着く
・攻撃的な症状が治る
・認知症の症状の改善
・身体機能の維持
心に寄り添うことで、安心・信頼などポジティブな感情を抱きやすくなります。
ケアを行う人
・精神的な負担が減る
・良好な関係を築くことでケアがスムーズに行えるようになる
ケアの無理強いがなくなり、罪悪感が少なくなります。
ユマニチュードを実践することで、認知症の患者さんのQOL向上はもちろん、ケアを行う人の負担軽減やモチベーションの向上にも期待ができます。
ケアの中に取り入れていくことは簡単ではない場面も多くありますが、できることから実践しケアに役立ててみてください。
参考:日本ユマニチュード学会
参考:メディカルジャパン
https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/blog/humanitude.html
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。