「脳科学者が認知症の母親の介護で得たものとは」【JTCAセミナー】
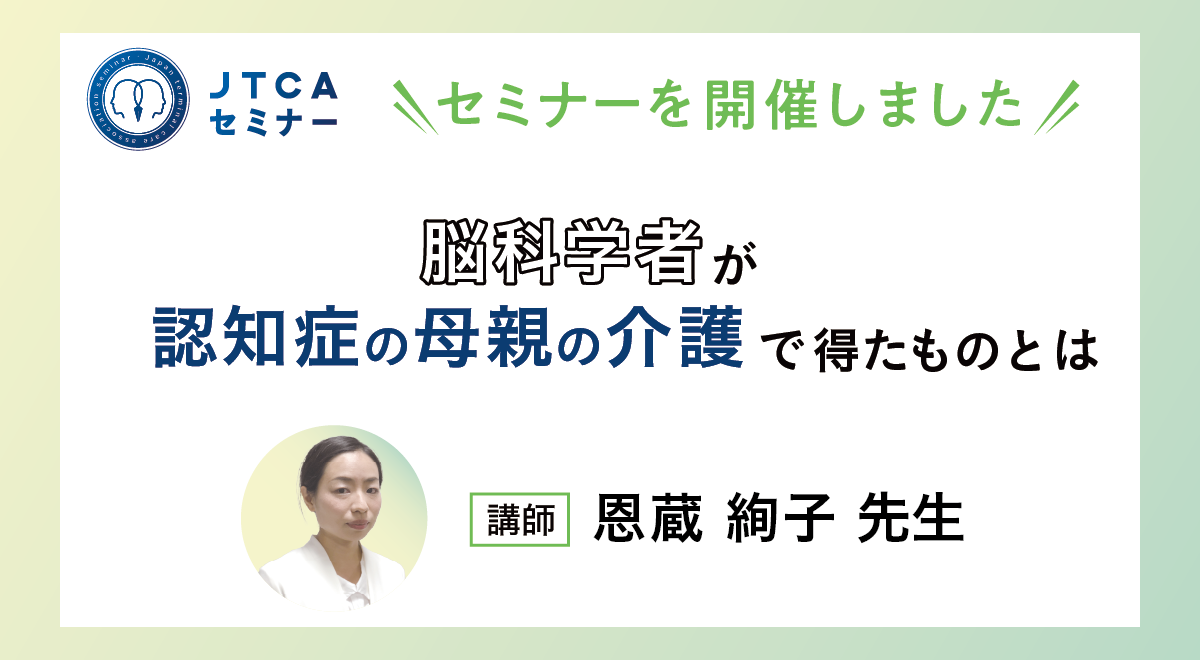
- 目次
2025年9月10日、JTCAセミナー「脳科学者が認知症の母親の介護で得たものとは」を開催しました。

講師
東京大学大学院総合文化研究科
特任研究員
恩蔵 絢子 先生
講義では脳科学者である恩蔵絢子先生がみた、認知症で障害される脳の機能とケアについてお伝えしていただきました。先生が認知症のお母様との関わりから得た気づきから、ケアについて一緒に考える非常に有意義なセミナーとなりました。
前半の講義では
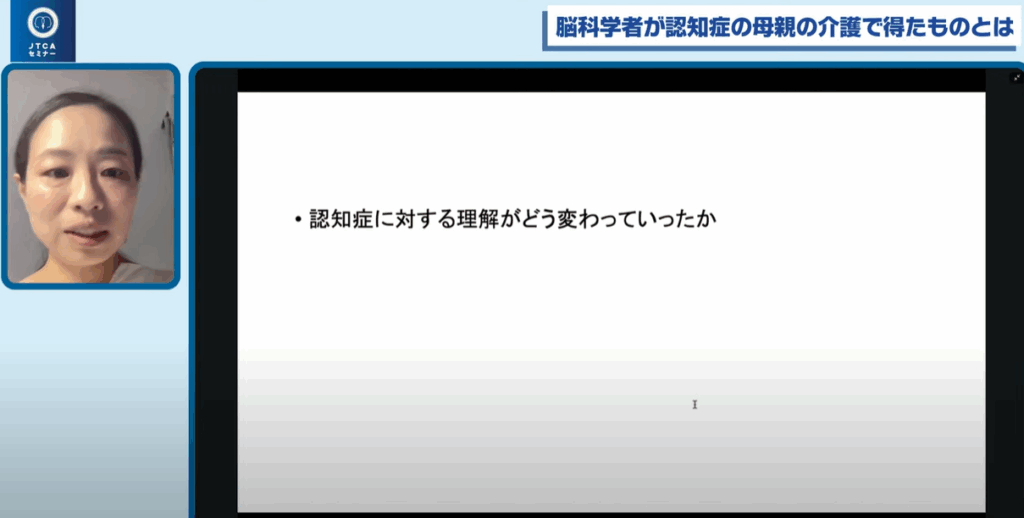
- アルツハイマー型認知症で人格が変わるといわれているのは本当か
- お母様の認知症に対する自身の受け止め方の変化、関わり方を脳科学的視点で説明
- 認知症はなにもわからない、理解できないのかと思われているが、脳の一部である海馬が傷ついているために現在(いま)のことが覚えにくくなっている。人としての感情はそのまま続いている
- 「できること」=能力 「その人らしさ」=感情
前半の講義では、これらについてお話いただきました。
後半の講義では
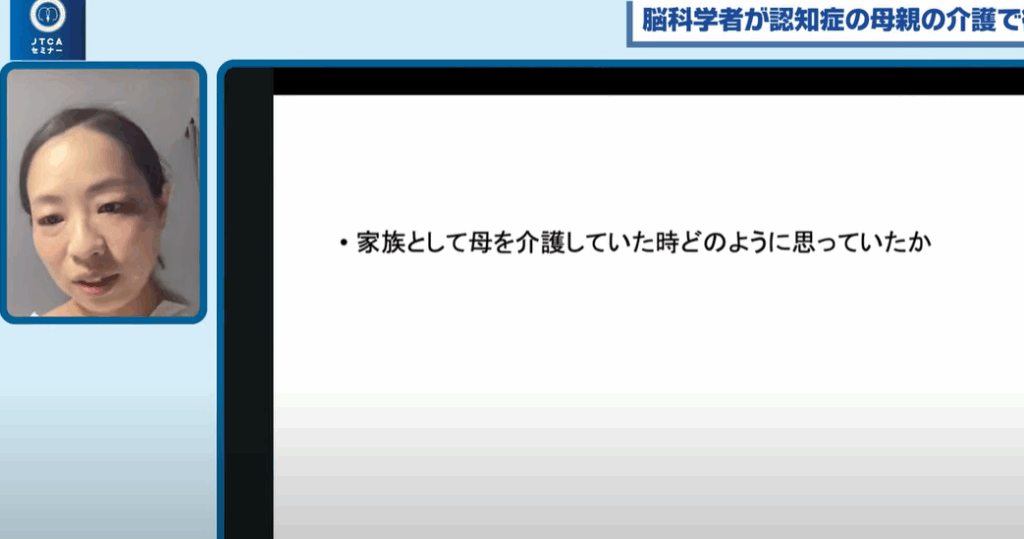
- 脳科学者である先生ご自身が家族として介護をする中でどのように思っていたのか、当時を振り返って今思うこと
- 脳の「共感回路」が働き、自分に近しい人であればあるほど相手の反応に左右され、冷静に見ることが難しい
- あえて「必要ではない時間を持つこと」で、お母様が自身の気持ちを発揮できる時間が生まれ、相手の気持ちをみることにもつながる
後半の講義では、これらについてお話いただきました。
講義を振り返って
今回のキーワードは「言葉で言えることだけを見ることは、本質を見逃すこと」です。思い出せなくても、身体が覚えており、感情はそのまま続いています。行動のプロセスを思い出せないだけであって、そこを手助けしていくことで、形を変えて何回でもその人らしさに繋がることができるということを教えていただき、認知症との関わり方について改めて振り返ることができました。
受講生の皆さまの感想
- Aさん
ご家族の話を、家族として、科学者としてお話してくださり、認知症の理解につながりました。感情は残るってそういうことなんだ、などなるほどと思えることが沢山ありました。ありがとうございました。 - Bさん
脳科学の知見から見た認知症の方の介護という自分たちには無い視点からのアプローチだったので、とても興味深い内容でした。自身の介護にも活かせる内容であったと感じました。貴重なお話ありがとうございました。 - Cさん
脳科学でのデータと個々の認知症症状とは少し違うことがわかり、大変ためになりました。 必要がない言葉や行動を意識してケアに臨めるようにします。 嫌なことを忘れても嫌だった感情は忘れないと言う言葉がとても印象的でした。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
