世界のケアをのぞき見!~グローバルナースとアメリカ・ハワイの終末期ケア~【学びLabo】
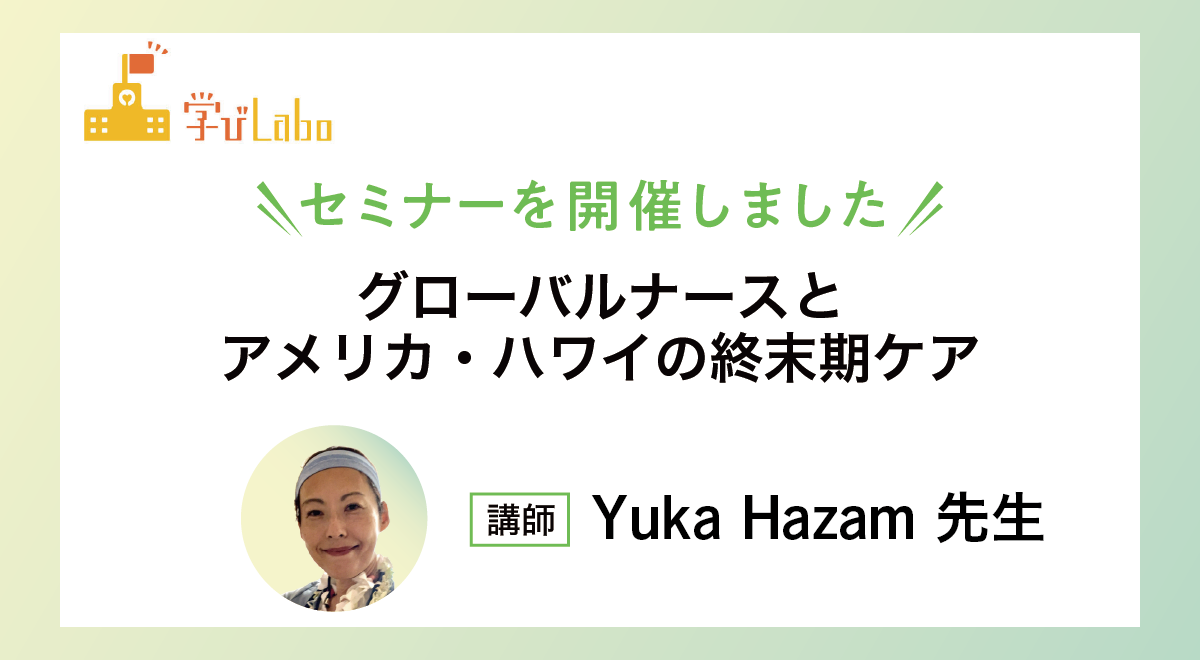
- 目次
2024年12月13日、学びLabo「世界のケアをのぞき見!~グローバルナースとアメリカ・ハワイの終末期ケア~」 を開催しました。

日本における終末期ケアについて、皆さんはどのように捉えているでしょうか。緩和ケアを必要とする患者や家族、そのケアを提供する医療・福祉・介護に携わる人によってそのイメージは異なると思います。
今回はハワイでグローバルナースとして働くYuka Hazam先生に現地の終末期ケアについて紹介していただきました。また、グローバルナースの視点から今後のケアに求められることについてもお話ししていただきました。
ハワイでの終末期ケアやグローバルナースの役割を知ることで、改めて日本の終末期ケアについて考えさせられる講義となりました。
講師
米国ナースコンサルタント・ベッドサイドナース
Yuka Hazam 先生
グローバルナースって?
ハワイの医療・看護の特性
グローバルナースとは
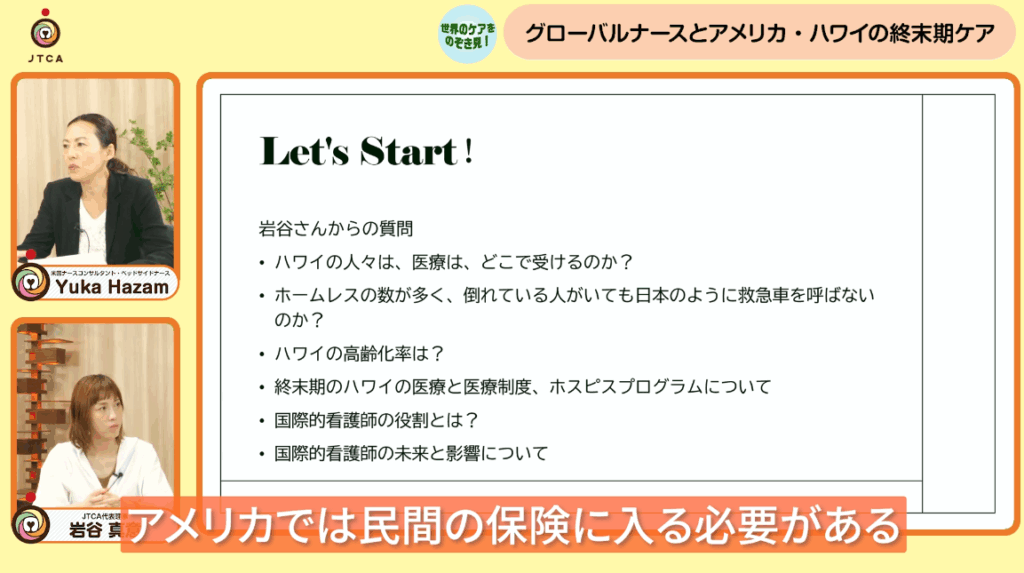
前半の講義では、アメリカ・ハワイの医療の特性を通して終末期ケアやグローバルナースについてお話ししていただきました。
日本には国民皆保険制度があり、国民は一定の自己負担額で医療を受けられる上、医療機関を自由に選ぶことができます。ハワイでは個人で民間の保険に加入することが必要です。そしてプライマリーケアクリニック(かかりつけ医)を受診し、必要に応じて専門医につないでいくシステムとなっています。そのため、すぐに病院にかからず必要に迫られて受診するケースもあります。
ハワイも高齢化が進んでおり、終末期ケアの必要性もさらに高まっています。そのケアの一つに、平均余命6か月以下の方を対象とした「ホスピスプログラム」というものがあります。6か月を超えても状態が安定していれば一旦退院し、終末期ケアが必要な人のために入れ替わることもあります。もちろん状態が悪化した場合は、再度ホスピスプログラムに戻ることも可能です。
日本の終末期ケアと大きく異なる点は、様々な言語やバックグラウンドを持つ人々が対象となるところです。そこで重要なのがグローバルナースの存在です。グローバルナースの役割は「言語・バックグラウンドの異なる人々に対し、安全で平等なケアを提供すること」とYuka先生はおっしゃっています。
コミュニケーションの重要性
ハワイの社会問題
ハワイと日本の看護師の違い
ハワイの終末期医療
グローバル看護を学ぶこと
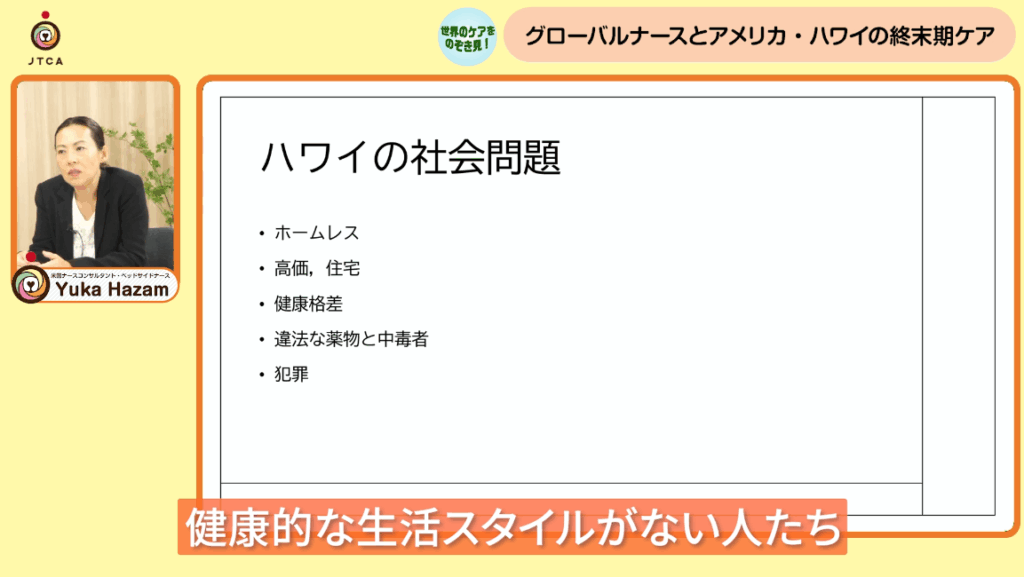
後半は、ハワイの歴史や社会問題に触れながらハワイと日本の看護師の違いについて比較し、ハワイでの終末期ケアとグローバル看護について学びました。
華やかなイメージのハワイですが、社会問題から日本人に対するネガティブな印象を持つ高齢者も少なくありません。また、物価の高騰や健康格差、違法な薬物や犯罪といった問題も抱えています。このような社会背景の中で求められる看護師像とはどのようなものでしょうか。
ハワイの看護師も患者と同様、様々な文化をバックグラウンドに持ち、多様性が認められます。会話で相手を理解していくというオープンなコミュニケーションスタイルが特徴的といえます。逆に日本の看護師は、きめ細やかで、空気を読む・察するコミュニケーションが得意といえるでしょう。
アメリカの終末期ケアはまだまだ人々に浸透しておらず、必要になって初めて知る場合も多いといえます。包括的である終末期ケアには時間がかかり、チームでのかかわりや多角的なアセスメントが重要となります。そのため、早期からエンドオブライフケアに取り組み、患者や家族が生死について考えていくことへの支援が求められます。言語・バックグラウンドの異なる人々に対し、安全・公平に看護を提供するためには、文化や言葉の理解、そしてコミュニケーション力が必要です。
Yuka先生は「あなたが医療を受けるうえで、私に知る必要があることはありますか?」と患者に問いかけ、患者の信頼と安心につなげることが大切だとおっしゃっていました。
講義を振り返って
日本においても医療を必要とする人々は、性別や年齢・人種も超えて多様化してきているのではないでしょうか。今回はハワイにおけるグローバルナースの視点を通して、言語やバックグラウンドの異なる人へのケアを学ぶことができました。
あなたのことが知りたい。そのうえで何ができるか考える。Yuka先生の温かい言葉が印象的な講義となりました。
参加した皆さまの感想
Aさん
本日は、ハワイの終末期医療についての講義ありがとうございました。ハワイでも、日本と共通した課題があるとなんだか安心しました。豊富な知識と経験での話は大変興味深く楽しかったです。
Bさん
宗教や文化の違いを知る事、自分に何が出来るか尋ねる事、心に留めておきたいと思いました。
Cさん
異文化の中で、医療というデリケートなサービスを提供することは、本当に大切だと思います。日本もどんどん個別化がおこってきており、「日本らしさ」というくくりはなくなってきているのではないかと感じています。今日は、違った視点から、日本の医療を考えさせられる講義でした。ありがとうございました。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
