終末期の食事支援とは~患者と家族のためのお食い締め~

- 目次
終末期看護の食支援とは
終末期看護をしていて、患者さんや家族から食事のことで相談されたことはありませんか?
または、自分自身が食支援に悩んだことはありませんか?
終末期においての食事の役割は、栄養補給だけでなく、患者さん自身にとっての生きる希望や唯一の楽しみという意味もあります。また家族にとっては、少しでも食べて長生きして欲しいという願いが込められたものでもあります。
しかし、それが時に衝突する原因にもなります。在宅であれば、家族が食事を提供することは、家族としての大きな役割や充実感を感じる支援の一つになっています。
そんな、いろいろな想いや希望が含まれている食支援は、一筋縄でいかないのが現実です。
「食べたいのに食べられない」
「食べさせたいのに食べてくれない」
「どう支援したらいいのかわからない」

みなさんも日々試行錯誤されていると思います。
それでも「最期に好きなものを食べさせてあげられなかった」と心残りになったケースもあるのではないでしょうか。
今回は、いろいろな食支援がある中で、「お食い締め」の観点に着目してみたいと思います。
お食い締めとは
みなさんは、「お食い締め」という言葉を聞いたことはありますか?
お食い締めとは
お食い締めとは、愛知学院大学歯学博士、言語聴覚士の牧野日和氏が作った造語です。
狭義には、「人生最後の食事」
広義には、「最期に誰と何を食べようか」などと食事に思いをはせることで、「周囲との絆を形成し、去り行くものと残されたものが、それぞれの立場で命を学ぶ機会を得ること」と言われています。
お食い締めがもたらす効果
①本人
・最期まで自分らしく過ごすことが出来たという満足感
・最期に好きなものが食べられたという満足感
・家族の希望を叶えてあげられたという満足感
・家族や友人と一緒に食事する時間を設けることで、時間や体験の共有が図れたことへの満足感
②家族
・最期に患者本人の希望を叶えてあげられたという達成感
・患者さんと一緒に食事する時間を設けることで、時間や体験の共有が図れたことへの満足感
・グリーフケアへ繋がる
③スタッフ
・患者さんや家族の支援ができたという達成感
・様々な食事支援の在り方を学ぶ機会
・様々な死生観を学ぶ機会
お食い締めの内容は十人十色です。患者さん・家族・スタッフ間で意見の相違も見られますが、お食い締めを行うことで、「最期まで自分らしく生きられた」「最期に好きなものが食べられた」という患者さんの満足感や達成感に繋がります。
そして、それは患者さんだけでなく、一緒に準備した家族にとっても「患者の希望を叶えてあげられた」という有意義なものになるのです。
お食い締めの進め方
お食い締めを行うにあたって一番大切なのは、コミュニケーションです。
患者さんとその家族と十分に話し合いを行い、進めていきましょう。
お食い締めの進め方
①食事支援の方向性について話し合う
患者さんや家族から食支援についての相談をされた際、どんな方法が一番いいのか話し合う。
②誤嚥のリスクの説明
摂食嚥下障害のある患者さんの場合、食事摂取することでの誤嚥のリスクについて医師から十分説明した上で、医師だけでなく言語聴覚士のサポートも得て実施する。
③食事の内容
食事の内容や形態については、嚥下評価をもとに管理栄養士などの専門職とよく話し合って決める。
④誰と一緒に食事するのか
最期に一緒に食事したい方を呼んでもらう。
面会制限の関係で会えない方は、可能であればタブレット越しで参加する、テレビ電話を活用するなどの工夫をする。
⑤どこで行うのか
どこで食べたいのか希望を確認する。
病室や談話室の場合、置きたいものや準備したいものがあるか確認する。
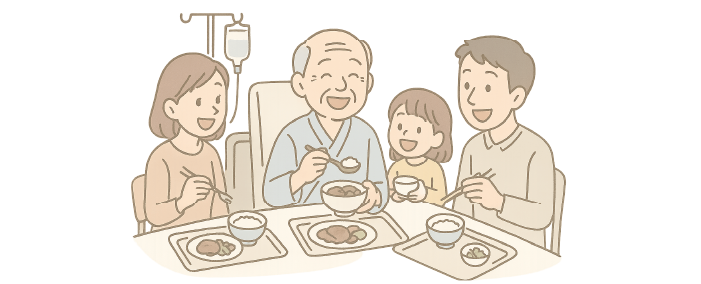
まとめ
日々の何気ない食事の中にも家庭ごとの様々な食文化が存在します。大切な思い出や懐かしい記憶の中には「特別な料理」も存在するでしょう。望んだ食べ物を最期に食べられたということは患者さんにとっては喜びであり、残される家族にとってもその喜んでいる姿は心に残るはずです。
患者さんと家族のそれぞれの想いに寄り添い、お食い締めを行うことは、単に患者さんの望みを叶えるだけでなく、残される家族にとってのグリーフケアにも繋がります。
終末期の食事支援に正解はありません。今回着目したお食い締めも多くの食事支援の一つにすぎませんが、それを通して患者さん・家族と一緒に考え、共に悩むその時間は大切なコミュニケーションとなります。そして看取りを終え、悲嘆にくれる中でも家族やスタッフと食事の思い出を語り合えることは、これから生きていく上での大きな糧となることでしょう。
参考文献
第2回 中編:「お食い締め」とは何か?ご家族が死を受容する過程に見た思いの変化【愛知学院大学 心身科学部 健康科学科・言語聴覚士 牧野 日和 先生編】 | リハノメ -gene’s info-
食べることが困難になる、摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)って何?〜言語聴覚士のお仕事〜 – 言語聴覚士のお仕事
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
