下顎呼吸 〜患者家族へ私たちができること〜
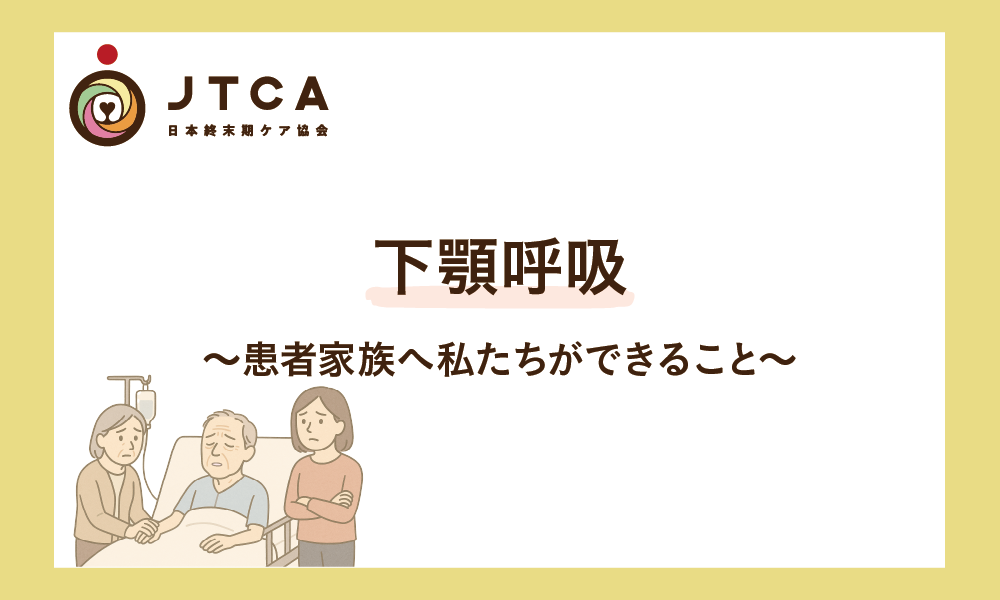
- 目次
死の直前に現れる「下顎呼吸」とは
死がせまってくると身体に様々な変化をもたらします。*表1
中でも、呼吸の変化は目に見えて変化がわかりやすく、また息苦しそうな様子から家族が不安になりやすい可能性があります。
呼吸の変化
・無呼吸と1回換気の強弱を交互に繰り返すチェーン・ストークス呼吸は死亡直前の多くの患者にみられます。
・胸の動きが小さくなり顎があがり喘ぐような呼吸の様子でほぼ換気ができていない状態を下顎呼吸と言います。これは心臓の機能や肺の機能が低下することによって低酸素になることで起こると言われています。
・呼吸の際に咽頭や喉頭に貯留した分泌物によりゴロゴロと音がすることがあります。これを死前喘鳴と言います。これは死亡直前になり呼吸そのものが弱くなると喘鳴が聞こえなくなることがあり、死前喘鳴が消失し下顎呼吸に移行します。この呼吸の一連の変化は死期が迫っていることを示します。
表1)死がせまっていることを示す徴候の分類:OPCARE9プロジェクトによる国際分類
| 呼吸の変化 | 呼吸リズムの変化(チェーン・ストークス呼吸)、下顎呼吸、死前喘鳴 |
| 意識・認知機能の変化 | 意識レベルの低下、昏睡 |
| 経口摂取の変化 | 食事・水分が取れない、嚥下障害 |
| 皮膚の変化 | 網状の皮膚(チアノーゼ)、色調の変化、四肢の冷感、口唇・鼻の蒼白 |
| 情動的な状態の変化 | 落ち着かなさ、身の置き所のなさ、精神状態の悪化 |
| 全身状態の悪化 | 身体機能の低下、臓器不全 |
| その他 | 医療者の直感 |
(出典:森田達也 白土明美,死亡直前と看取りのエビデンス 第2版,医学書院,2023,p6 表2.)
下顎呼吸がみられたとき、私たちができる家族ケアとは
前述したように呼吸は目に見えてわかる変化のひとつです。目の前の家族の状態が目に見えて変化するとどれだけ事前に説明していても、とても不安になる家族もいらっしゃいます。そんな時、わたしたちはどのように声掛けをしていけばよいのでしょうか。
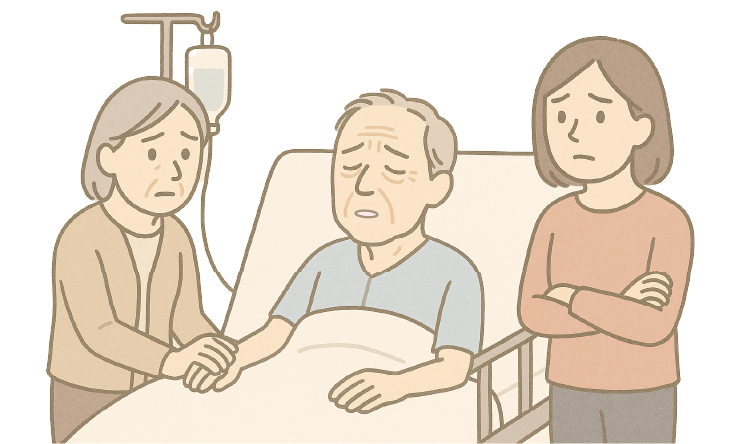
わたしたち医療者にとって死は身近なことが多く、医療職以外と比べると亡くなる人をみる機会は多くあります。しかし、医療職以外の人にとって死はどちらかというと遠い存在であり、意識して暮らしている人は少ないと言えるでしょう。そのような人たちが死と直接関わるのは家族などの死であり、その機会は多くはありません。
そのような人たちに亡くなる前の徴候について事前に説明していても、いざそういった場面に直面すると動揺することが容易に想像できます。事前に説明していたから大丈夫だろうや受け止められるだろうといった考えではいけません。受け止められなくて当たり前、動揺して当たり前という視点を医療者側が持つことが大切です。
家族から下顎呼吸について問われた際は、亡くなる前のほとんどの人がなる呼吸の様子であり、自然なことだと説明してあげることで家族の不安の軽減にも繋がります。また、現れた症状に対して家族へ説明することも不安の軽減につながります。
下顎呼吸がみられてから数時間で亡くなることも多くみられるため、家族が患者のそばにいないときは、死期が間近に迫っていることを家族へ連絡することも家族へのケアに繋がります。いつ家族へ連絡すれば良いかに正解はありませんが、家族がそばにおらず連絡を望んでいるのであれば下顎呼吸がひとつの指標になるでしょう。
参考文献
1)森田達也 白土明美,死亡直前と看取りのエビデンス 第2版,医学書院, 2023,312p.
2)一般社団法人日本終末期ケア協会,終末期ケア専門士 公式テキスト第2版,p.236-243.
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
