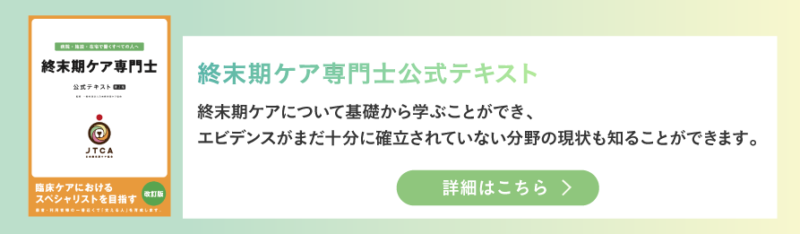せん妄とは?認知症・うつ病と比較してみよう!
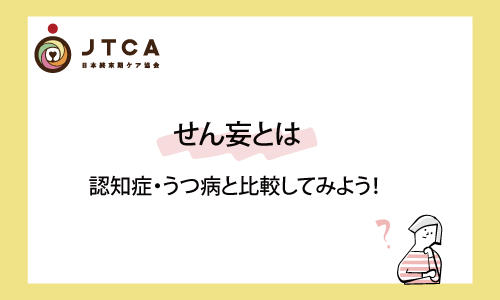
- 目次
【目次】
2.せん妄の主な症状
3.せん妄の現れ方
4.認知症とうつとの違い
5.せん妄の症状と種類
6.終末期せん妄とは
7.せん妄の原因
8.せん妄は予防できるのか
9.せん妄に対する薬物治療
10.せん妄に対する非薬物療法
11.家族ケア
せん妄は精神障害なのか?
「今日の夜勤はせん妄の人が多いよ」と聞くと、
誰もが「忙しい、大変そう」という
イメージを抱くでしょう。
コミュニケーションがとりにくいこと
行動パターンが予測できないこと
終わりが見えないこと、などは
現場で働く人にとって
ストレスの要因となります。
医師を中心としたチームで相談しても、
適切な対応法を見いだせないこともあるでしょう。
まず、私たちが正確にせん妄状態について
理解することが大切です。
せん妄とは、身体疾患や薬物などの
影響により生じる意識障害の一種で、
急性の脳機能障害という「状態」です。
せん妄には、治る可能性のあるせん妄と
治る見込みが持てないせん妄があります。
まずは、検査や病状評価、環境分析を行い
原因を特定します。
そのうえで、治療方法が
あるかどうかを見極めます。
せん妄の主な症状
せん妄とは、身体疾患や薬物などの
影響により生じる意識障害の一種で、
急性の脳機能障害という「状態」です。
これに伴い精神状態の変化や変動、記憶欠損、
失見当識、言語障害などの
認知機能障害、注意力障害、および思考の混乱
または意識レベルの変化がみられます。
随伴症状として、睡眠覚醒リズムの障害、
幻覚や妄想、精神運動異常や恐怖、
不安、怒り、うつ、無感情、多幸症などの
感情の変動があります。
せん妄の現れ方
————
☑急性に発症し数時間から数日単位で症状が変化する
☑夕方から夜間にかけて増強する
☑せん妄でみられる妄想は一過性であることが多い
————
が挙げられます。
認知症とうつとの違い
認知症は、
・徐々に進行し、急激に症状が発症することはない
・記憶障害が目立つ
うつは、
・発症は個々で異なるが、緩徐である
・昼間(午前中)に症状がでやすい
・認知機能は障害されにくいため、見当識障害や記憶障害はみられにくい
認知症やうつと症状が類似しているため
間違えて認識される場合があるので
注意が必要です。
せん妄の症状と種類
過活動型せん妄と認知症、低活動型せん妄と
うつ病は、それぞれ症状が似ているため
間違われることがあります。
終末期せん妄とは
終末期に生じる
治療困難なせん妄のことをいいます。
終末期せん妄は、過活動型の場合も
低活動型の場合もあります。
がん患者の
約70%が終末期せん妄を体験すると
いわれており、終末期によくみられる
症状であるといえます。
終末期せん妄による幻覚など、
苦痛を伴う体験も
多いため、せん妄症状の改善を
目指したケア介入が重要となります。
せん妄の原因
せん妄は>準備因子・促進因子・直接因子の
3つの因子が
複雑に絡み合って引き起こされます。
▪準備因子は、せん妄を引き起こす素因となるもので、素因がないか確認していくことが必要です。
▪促進因子は、せん妄を誘発しやすく、悪化や遷延化につながる要因となるため除去に努めます。
▪直接因子は、せん妄の直接的な引き金となる要因であり、直接因子を把握し、改善が見込めるものについては対策を講じることが必要です。
特に終末期には原因が複数絡んでいることが
多いため、治療が可能かどうかの見極めが
不可欠となります。
【準備因子】
高齢 認知症 脳器質性疾患の既往 アルコール多飲 せん妄の既往
【促進因子】
身体的苦痛(不眠 疼痛 便秘 尿閉 視力・聴力障害 身体拘束など)
精神的苦痛(不安 抑うつ 身体拘束など)
環境の変化(入院 集中治療室 騒音など)
【直接因子】
身体疾患 薬剤性 手術 アルコール(離脱)
せん妄は予防できるのか
せん妄を引き起こす3つの因子を取り除くことで
せん妄を予防し、悪化を防ぐことができます。
特に、最も身近にいる看護師や介護士の観察や
かかわり方が重要となってきます。
せん妄に対する薬物治療
せん妄には、回復を目標とする
「可逆性せん妄」と、
回復が望めないため苦痛緩和を目標とする
「不可逆性せん妄」があります。
せん妄では、その原因を取り除くことが
可能かどうかによって、治療目標が異なり、
使用する薬物も違います。
せん妄と診断されれば、まず原因に対する
アプローチを行い続いて、必要に応じて
薬物療法を検討します。
可逆性せん妄では、せん妄からの
回復を目指して抗精神病薬を使用しますが、
不可逆性せん妄では
苦痛軽減のため抗精神病薬や
医療用麻薬を使用することがあります。
不眠の治療薬として、ベンゾジアゼピン系薬が
処方されることがありますが、せん妄を発症する
リスクが高いため使用を控えることが望ましいです。
せん妄に対する非薬物療法
▪昼夜のメリハリをつけるなど照明の調整
▪生活リズムを整える
▪排尿、排便、口渇などの基本的ニードの充足
▪痛みや発熱など身体的苦痛の確認
▪眼鏡、補聴器の使用
▪日時や場所を意識した声かけを行うなど見当識への支援
▪自宅で使用していたものを持参する、写真を飾るなどなじみのある環境をつくる
▪活動する時間帯の点滴を避ける、活動の妨げにならないようルート類の管理
▪落ち着いたコミュニケーション
▪障害物や危険物の除去、見守りやすい部屋にするなど部屋の安全確保
家族ケア
せん妄ケアは、本人へのケアだけでなく
家族へのケアも大変重要となります。
家族の多くは、いつもと様子が違い、
人が変わったように見える患者の姿を
目の当たりにしショックを受け、
どのように接したらよいのか
分からず困惑してしまいます。
したがって、家族の気持ちに寄り添うこと、
コミュニケーションで注意が必要なことを
分かりやすく伝え、せん妄についての
正しい情報を伝えることが大切です。
また、せん妄症状の改善のために
薬剤を使用することもあります。
ご家族の中には、向精神薬、睡眠薬、
医療用麻薬などの使用に
不安を抱くこともあります。
薬剤に期待される効果、呼吸抑制や
過鎮静などのリスクについても
家族に伝え対策を検討していくことが必要です。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。