「できることから始めよう~地域緩和ケアの推進の担い手として~」【学びLabo】
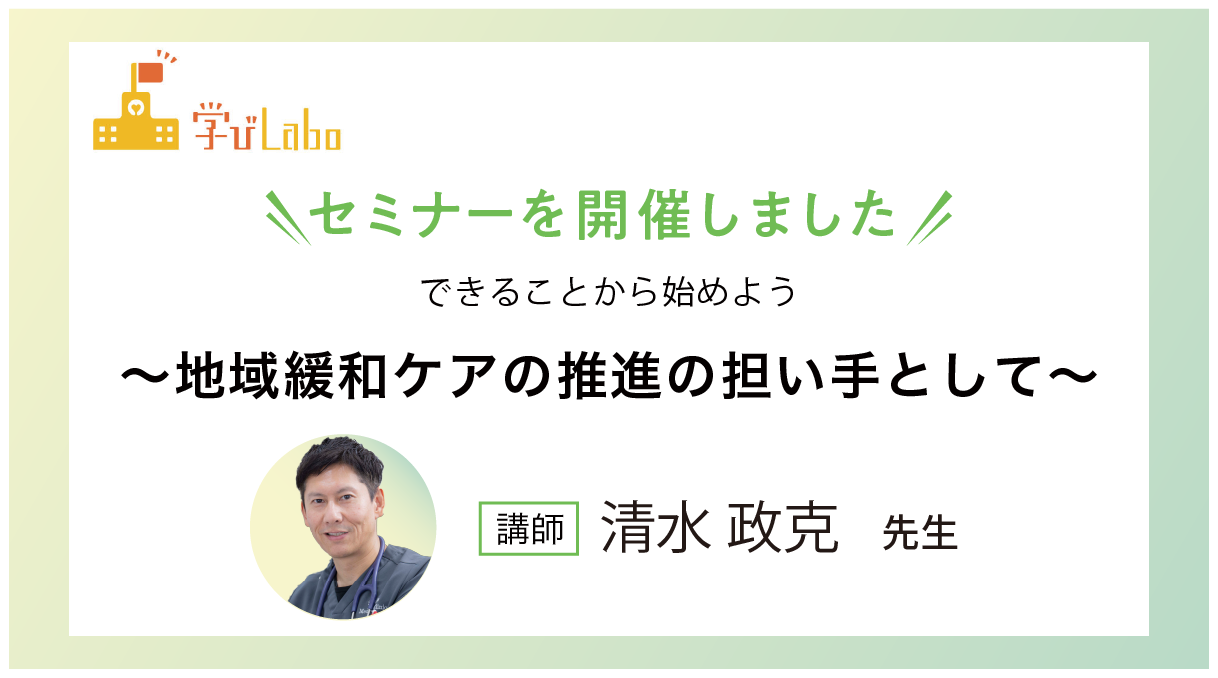
- 目次
2025年6月17日、学びLabo「できることから始めよう~地域緩和ケアの推進の担い手として~」 を開催しました。
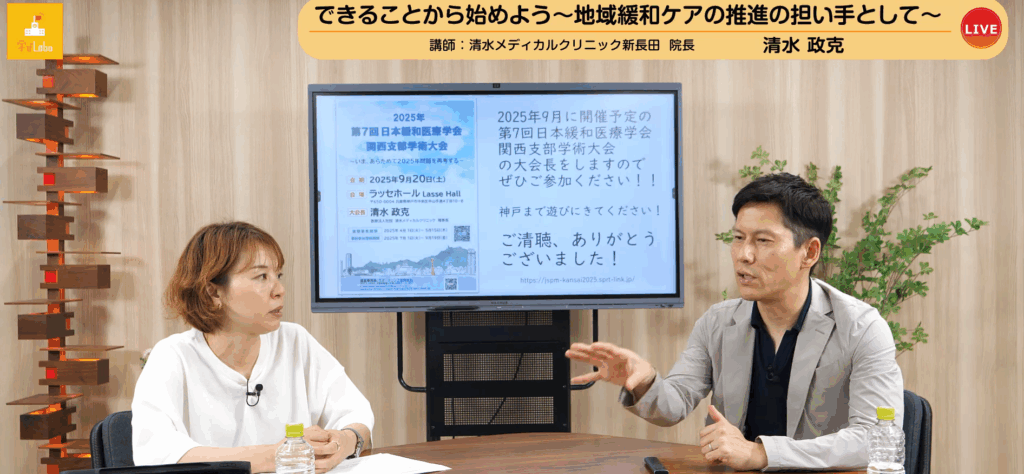
講師
医療法人社団 清水メディカルクリニック 理事長
清水メディカルクリニック新長田 院長
清水 政克 先生
前半の講義の紹介
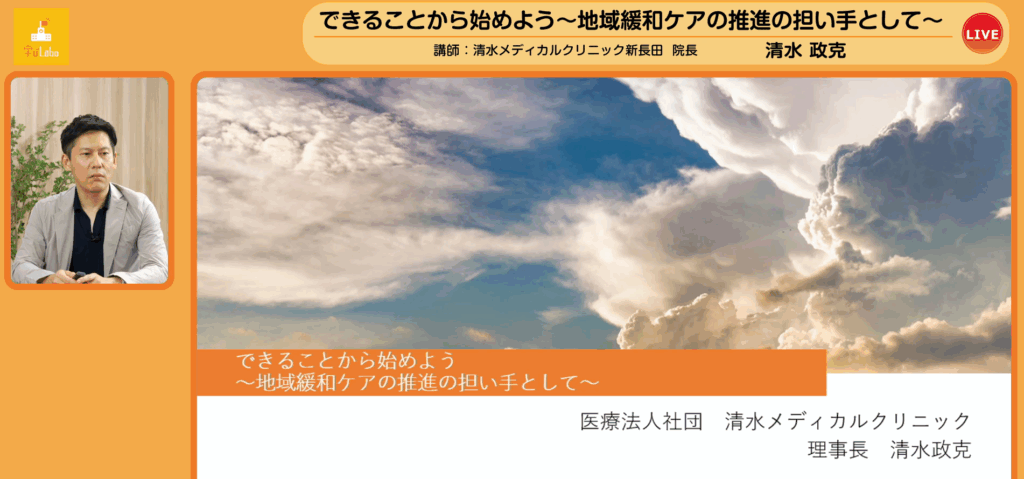
前半は以下について講義していただきました。
多職種で連携し地域づくりをしていくために
・地域で生きていくためには、退院後も安心して生活できるような支援が必要です。その一つに医療的ケア児の支援があります。医療的ケア児の診療に積極的に取り組み、看取りになったとしても、在宅で過ごすことができるということを地域に広めていっています。在宅で看取る前から家族ケアを開始したり、お看取り後の家族が参加できる遺族会の開催をしたりすることでグリーフケアにも繋げています。
・現場で働く人が自信を持ってケアができるように、実際にケアを体験できる場を設けたり、勉強会をおこなったりしています。
・一つの事例をとっても、職種が違えば見える視点が違い様々な意見が出ます。医療職だけでなく、弁護士や葬儀屋などといった多職種と交流する場を設け、多角的な視点から事例を考えることができるようにしています。
・職種をまたいで日常のケアの困りごとを話せる場をつくることで、「顔の見える関係」から「腹の見える関係」へとさらなる信頼関係の構築に繋がります。
・自宅で過ごすために、どのような職種に繋ぐ必要があるのかを知識としてもっておくことも大切です。
後半の講義の紹介
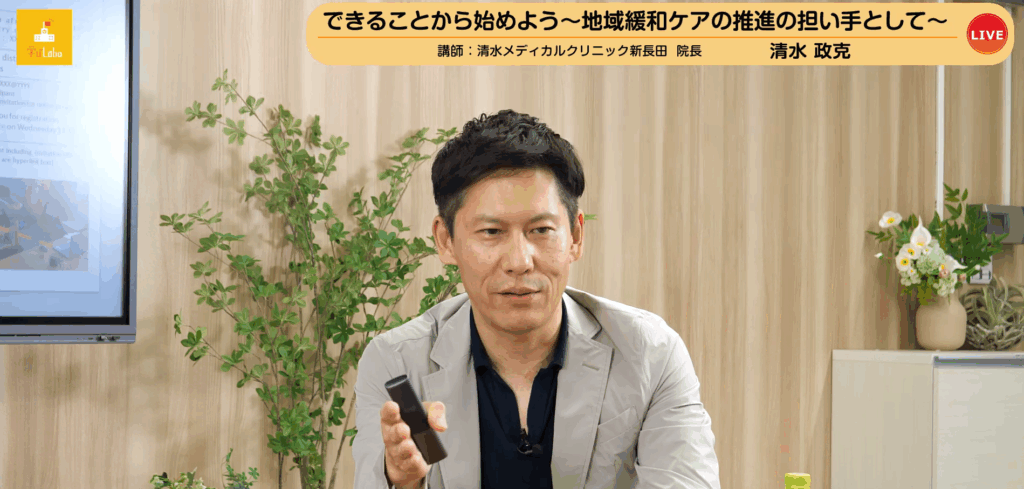
後半は以下について講義していただきました。
「安心感」を提供できる人材育成
・ケアをする人が安心感を提供するためには、人材育成が重要です。地域で暮らす患者が安心して過ごせるためには、しっかりしたスキルを持つ人材の育成が大切になってきます。
・在宅での看取りを経験するプログラムは、「こんな状態では家に帰れません」と言うことがないような医師の育成を目的としています。「最期まで家で過ごせます」という言葉のもとで患者が在宅で安心して最期を迎えられるような環境づくりをしています。
講義を振り返って
今回は自宅に帰る、地域で過ごすためには人それぞれの背景を持った日常があるということを改めて考えさせられる講義となりました。空き家の問題などの例も出てきて、地域で過ごすためには医療者だけではなく様々な職種の協力や連携が必要であることがとてもよくわかる講義でした。
講義の最後には対談形式で地域医療について伺いました。家庭医・在宅医に興味を持つ医師が最近は増えており、在宅目線で考えることができる医師が増えることで連携のしやすさに繋がることが対談を通してわかりました。学生や看護師なども地域医療について興味をもつ人が増えており、様々な職種を通して人材育成に繋がっていることも興味深いお話でした。
地域で「安心感」を持って生活していけるために、多職種が知識を得て多角的な視点を持ち関わっていくことが大切だと感じられる有意義な講義となりました。
参加した皆さまの感想
Aさん
他職種の理解が出来ないと多職種連携は難しいと日頃から感じています。それぞれの特性があるので話し合いを重ねていくことで患者さんやご家族への支援が図れると改めて感じました。ありがとうございました。
Bさん
多職種連携の大切さはもちろん、もしもの時がきた時の家族の行動について丁寧に説明し、知ってもらうことが大切だとあらためて思いました。これから私もたくさん勉強していきたいと思います。
Cさん
多職種連携として、ケアマネジャーと連携をとることはあります。それだけでなく地域として、不動産や葬儀屋等のたくさんの職種と連携することもあると知り驚きました。
初めて聞くことも多く、自分の視野・考え方はもっと多角的に見なければいけないと考えさせられました。ありがとうございました。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
