終末期の褥瘡~治療を助ける外用剤の使い方~
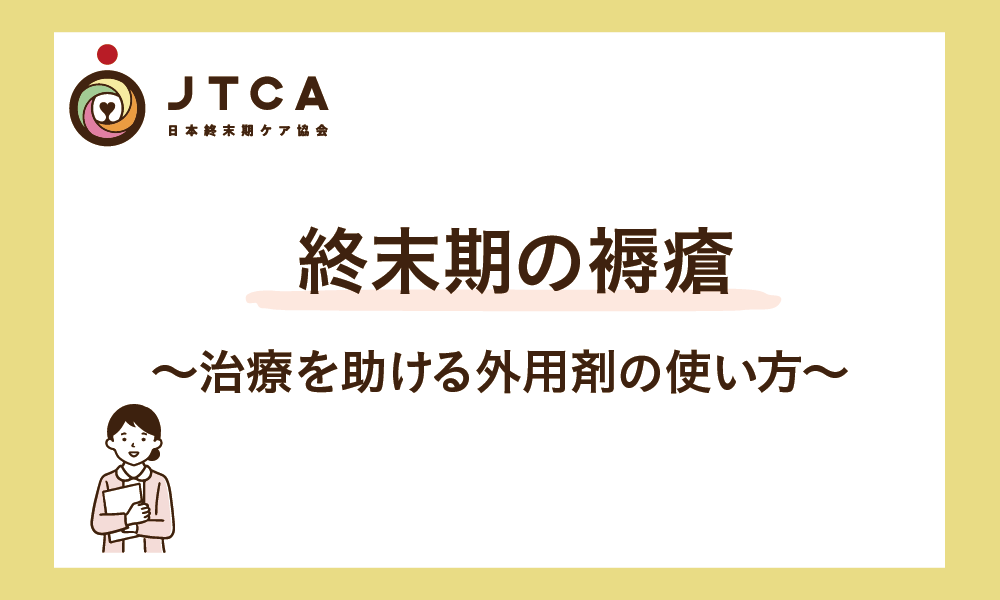
- 目次
目次
外用剤について
基剤の特徴と分類
主薬の特徴と種類
外用剤について
まず大前提として褥瘡は作らせないことが基本です。褥瘡予防のために体圧管理や栄養管理、皮膚の管理を行います。褥瘡発生は身体機能の低下との関連が高い病態です。しかしながら終末期を迎える状態は人によってさまざまで、タイムリーな介入時期の見極めやアセスメントはとても難しいと考えられます。そのように予防をおこなっていても、褥瘡ができてしまうことがあります。その場合は治療を行うことになります。褥瘡治療には、保存的療法(外用剤や創傷被覆材(ドレッシング材))、物理療法、外科的治療に分けられます。褥瘡診療ガイドライン(2023)に沿い、適宜アルゴリズムを使用しながら適切な治療がすすめられます。今回はその中のひとつである外用剤について学んでいきます。
外用剤にはさまざまな種類があり薬理作用を知り創の状態に沿った適切な選択をする必要があります。
外用剤 褥瘡の治療に使用する外用剤には様々な種類があります。創部に感染があるときに使用できるものや感染が落ち着いた後に創部の肉芽形成や上皮化を促すもの、保湿により創部を保護するものなどさまざまです。外用剤は、主薬と基剤からできており主薬は薬効成分のことをいいます。ステロイドや抗生物質などの薬剤の効果を発揮する部分です。一方、基剤には薬効成分はなく配合されている薬剤が効果を発揮しやすいように、薬剤を保持する役割があります。創の治癒には湿潤環境が重要であり、この湿潤環境の保持に基剤の役割は欠かせません。外用剤を選択する際には、基剤についても知っておくことでより適切な選択ができます。
基剤の特徴と分類
基剤は疎水性基剤(油分だけでできており水となじまない)と親水性基剤(水と親和性が高い)に分けられます。
【疎水性基剤】は油分だけでできているため少量の浸出液を創面に留めることができ、保湿効果や創の保護効果があります。創の上皮化に使用される基剤です。
【親水性基剤】は水と親和性が高く、水と油を界面活性剤で混じた乳剤性基剤と水分を吸収して溶解する水溶性基剤に分けられます。乳剤性基剤は水分の中に油を含む水中油型(O/W型)と、油分の中に水分を含む油中水型(W/O型)に分けられます。水中油型(O/W型)は乾燥した創面に水分を補給するものであるため、滲出液の少ない乾燥した創面に適しています。含有する水分が少なく補水機能が弱い油中水型(W/O型)は、滲出液が適正な創に用いられます。
水溶性基剤は水分を吸収して溶解するもので、滲出液を吸収するため滲出液の多い創に適しています。
主薬の特徴と種類
主薬に期待される薬効は①壊死組織の除去作用②抗菌作用③肉芽形成・上皮化作用④その他の作用であり、薬効に応じて薬剤の選択と使用をしていく必要があります。
一例)
①壊死組織の除去作用:カデキソマー(カデックス®軟膏)とタンパク質分解酵素(ブロメライン軟膏)
②抗菌作用:ヨード系化合物(カデックス®軟膏、ユーパスタコーワ軟膏など)、銀を含む(ゲーベン®クリーム)
③肉芽形成・上皮化作用:トラフェルミン(フィブラスト®スプレー)、トレチノントコフェリル(オルセノン®軟膏)、ブクラデシンナトリウム(アクトシン®軟膏)など
褥瘡の状態の評価として用いられるスケールとしてDESIGN-R®2020があります。大文字を小文字にしていくような薬剤の選択をするようにこころがけましょう。
外用薬は薬効や基剤の違いによってそれぞれの特性があります。創部の状態により適切な薬剤を使用することで、より効果的なケアにつながります。また治療において大切なことのひとつに洗浄があります。どれだけ適切な外用剤の選定をしても、創部やその周りが汚れていては効果が下がります。創部とその周囲を丁寧に洗浄し、清潔を保持することでより治療の効果が高まります。せっけんを使用する際は泡でやさしく洗い、せっけんが残らないようにしましょう。
まとめ
褥瘡は発生させないことが大前提ですが、終末期となれば体位変換が困難になったり身体機能の低下などさまざまな理由により、どれだけ予防していても発生することがあります。褥瘡が発生したときに、適切な対応ができるように知識を持っておくことが重要です。医師や看護師、介護士などそれぞれが知識を持っていることが患者さんのケアをよりよいものにできます。
参考文献
1)日本褥瘡学会.「褥瘡の治療について」.(最終アクセス:2025年8月14日)
2)日本褥瘡学会.「DESIGN-R®2020 褥瘡経過評価用」.(最終アクセス:2025年8月14日)
3)真田博美監修,石澤美保子・玉井奈緒編集.『終末期の褥瘡』.2025,177p.
4)ディアケア.「新まるわかり褥瘡ケア」.(最終アクセス:2025年8月14日)
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
