イギリスで可決された安楽死法案から考える日本の「安楽死」と「尊厳死」
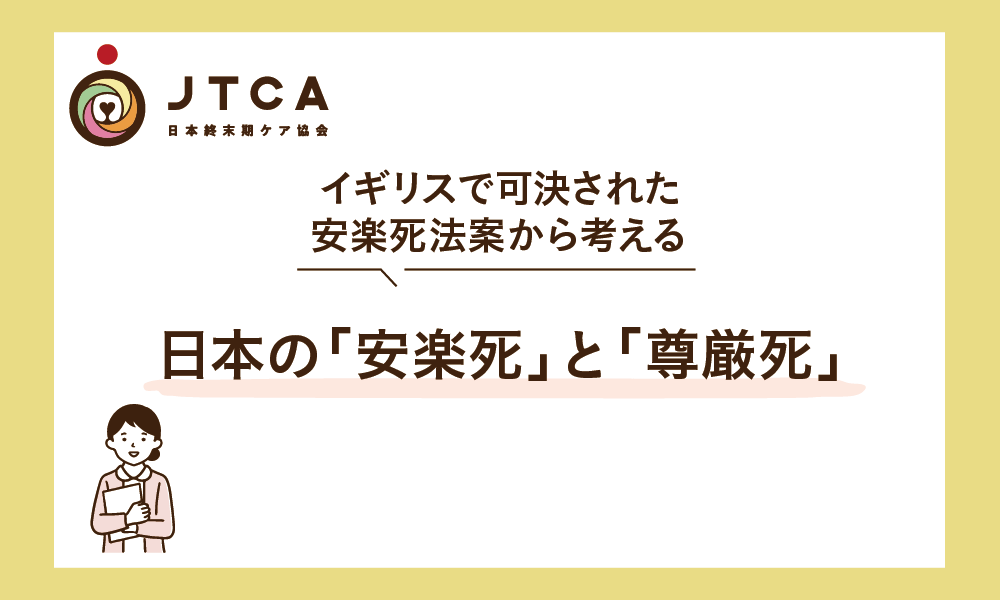
- 目次
安楽死法案が可決されたイギリス
2024年11月、イギリス議会で「安楽死法案」が賛成多数で可決されたのをご存じでしょうか。
この法案は、イギリスのイングランドとウェールズで、余命6か月未満と診断された18歳以上の成人が医師2人と裁判官の承認を得た上で、薬物の投与などによって死を選ぶ権利を認めるもので、2024年11月29日議会下院で行われた採決の結果、賛成多数で法案は可決されました。
可決された法案は今後、再度検討・審議され、法律となるかが決まります。
世界の安楽死を合法化している国
安楽死を合法化している国の中で、もっとも進んでいるのがスイスです。
スイスではすでに終末期患者に限らず、難病患者などに対しても「死ぬ権利」が認められています。また、外国人を受け入れているのも世界でスイスだけになります。
積極的安楽死と医師幇助自殺の両方を容認している国
オランダ、ルクセンブルク、ベルギー、カナダ、オーストラリアの一部、ニュージーランド、スペインなどの国と地域
消極的安楽死を容認する国
イタリア、アメリカ50州と1特別区、ドイツ、イングランド、オーストリアなどの欧州諸国、アジアではインド、タイ、台湾、シンガポールなど
韓国でも2018年に延命治療を中断する法律が成立
「安楽死」と「尊厳死」とは
ここでまず、安楽死と尊厳死のそれぞれの意味についておさらいしてみましょう。
安楽死とは
安楽死とは、患者が病気や怪我などから回復の見込みが無くなった場合や、「死」以外に人間らしさを保つ方法がないと判断される場合に、苦痛から解放されるために意図的にもたらされる死のことです。
安楽死にはいくつかの種類があり、その中で主な3つをここでは記載します。
消極的安楽死
消極的安楽死とは、怪我や病気で苦しむ期間を長引かせないために延命治療を中止し、死期を早めることです。延命のためだけの治療を中止して患者の苦痛を緩和させ、尊厳を保ちながら死を迎えることを目的としています。
間接的安楽死
間接的安楽死とは、怪我や病気の苦痛を緩和させる行為が副次的な結果として死期を早めることです。患者の苦痛緩和が主な目的となります。
例として、強力な鎮痛剤や鎮静剤の使用により苦痛を軽減しつつ、その副作用として生命機能が低下してしまうものです。
積極的安楽死
積極的安楽死とは、怪我や病気の苦痛をいち早く免れさせるため、意図的に死期を早めることです。治療法がなく、耐えがたい苦痛に苦しむ患者が自らの意思で死を望む場合に実施されます。
尊厳死とは
尊厳死とは、その人がその人らしく、人間としての尊厳を保ったまま死に至ることです。患者の意思に基づいて延命処置は施さず、自然に迎えた死を指す意味もあります。
広義の尊厳死という言葉には、死ぬ瞬間のことに加えて自然に死ぬという選択をした後に、死ぬまでの間の自分らしく生きていく時間も含まれます。
安楽死と尊厳死の違いとは
安楽死と尊厳死は、延命のための治療をしないという点では共通していますが、根本的に異なる点は、意図的に寿命を縮めるかどうかです。

安楽死・尊厳死の課題とは
では、なぜ日本では安楽死や尊厳死が進まないのでしょう。
そこにはいくつかの課題がありました。
①法の拡大解釈
安楽死を合法化すると、その適応範囲が広がり、意図しないケースでも安楽死が選択されるリスクがあります。例えば、高齢者や社会的に弱い立場の人々が、周囲の圧力や経済的理由から安楽死を選ばざるを得ない状況に追い込まれる可能性も考えられます。
②医師による判断のばらつき
いくらガイドラインを作成しても、医師個人の判断に任せることで、同じような状況であっても「耐え難い状況」と判断するのにばらつきが生じることへの懸念がなされています。
③難病患者の想い
終末期の苦痛や絶望を抱える難病患者にとって、安楽死は尊厳ある最後の選択肢となりえるかもしれません。一方で、安楽死制度が認められることで、自分と同じ疾患の患者が安楽死を選択した場合、プレッシャーを感じることもあるかもしれません。実際に、「安楽死しないのなら、自分で選んだ苦しい生き方を受け入れなさいと思われそう」「家族に介護で大変な思いをさせるぐらいなら死んだ方がいいのか」といった難病の方の意見もあります。
④倫理的または宗教的な視点
宗教によっては、安楽死を容認していない方々もいます。一方で、倫理的には患者の苦痛を和らげるために安楽死を支持する意見もあります。
⑤医療従事者の負担
安楽死の実施には、少なからず医療従事者に対して精神的、倫理的な重圧をもたらします。
⑥高齢化社会
高齢により自己決定の能力の低下した人は、本当に安楽死を望んでいるのか、判断が難しくなります。
日本における安楽死・尊厳死
すでに欧米諸国では尊厳死を合法化している国もある中、日本では法律上、尊厳死は認められていません。
しかし、延命治療の中止に関するガイドラインはすでに存在しています。本人と家族、医師による議論と合意形成がなされれば、延命治療の中止を含めた判断が出来ることが示されています。2014年には日本救急医学会や日本病院会が、中止できる延命治療についての提案を行っていますが、その判断を担保する法律ではありません。
では、日本では緩和医療しか選択肢はないのでしょうか。
リビング・ウイルとは
尊厳死宣言書「リビング・ウイル」はご存じでしょうか。
これは、公益財団法人日本尊厳死協会から発行されているものです。「人生の最終段階における医療・ケアを自ら選択する権利が保障され、最期まで自分らしく尊厳を保って生きることができる社会の実現を目指す」ことが目的で、回復の見込みがない状態になった時に延命治療を受けない意思を文書に示すものです。
それならDNARと一緒ではないかと思われるかもしれません。
DNARとリビング・ウイルはともに患者の治療拒否に関するものです。しかし、リビング・ウイルは本人による意思表明であり、DNARは心肺蘇生措置を求めない患者の希望についての医師の指示という違いがあります。
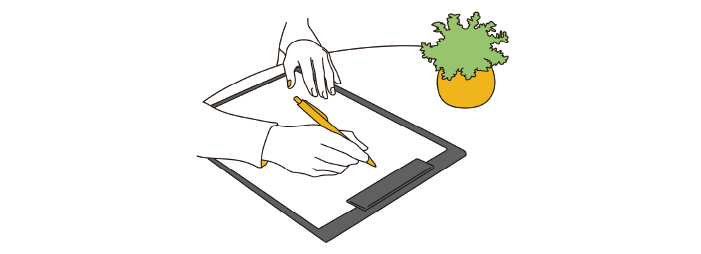
最後に
日進月歩で進歩していく医療の中、日本は他に類を見ない超高齢社会となりました。
緩和医療も日々進歩し、身体的苦痛の緩和だけでなく、全人的苦痛の緩和、最後まで自分らしく生きる、QOLの向上など、終末期医療や緩和医療でも様々な方向から患者を支援する体制が整えられています。しかし、長く生きることだけが幸せなのだろうか、緩和医療だけでは救いきれない患者の想いもあるのかもしれないと考えさせられます。
「死ぬ権利は、一体誰のものだろう」
何が正解で、何が間違いなのか、一概には言えない安楽死と尊厳死の問題は、これからも考えを止めてはいけない課題なのではないでしょうか。
参考文献
安楽死や尊厳死の特徴とは?日本の現状や問題点を解説|小さなお葬式
安楽死とは? 認められている国や日本と世界の現状 | ELEMINIST(エレミニスト)
英国は「安楽死」を合法に!なぜ日本は「尊厳死」さえ法制化せず、老人虐待を続けるのか?(山田順) – エキスパート – Yahoo!ニュース
一般社団法人 日本救急医学会 日本集中治療医学会 日本循環器学会
info-20141104_02_01_02.pdf「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について |報道発表資料|厚生労働省
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。
