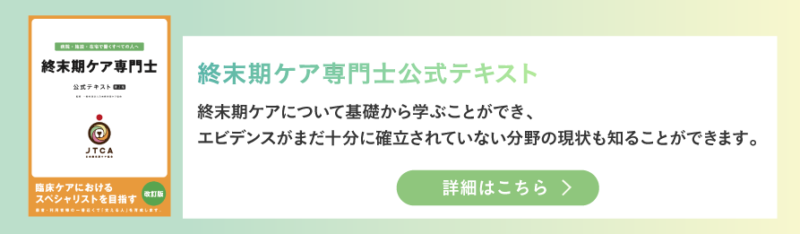終末期であっても日常の中に「ハレの日」を!【JTCAゼミ】
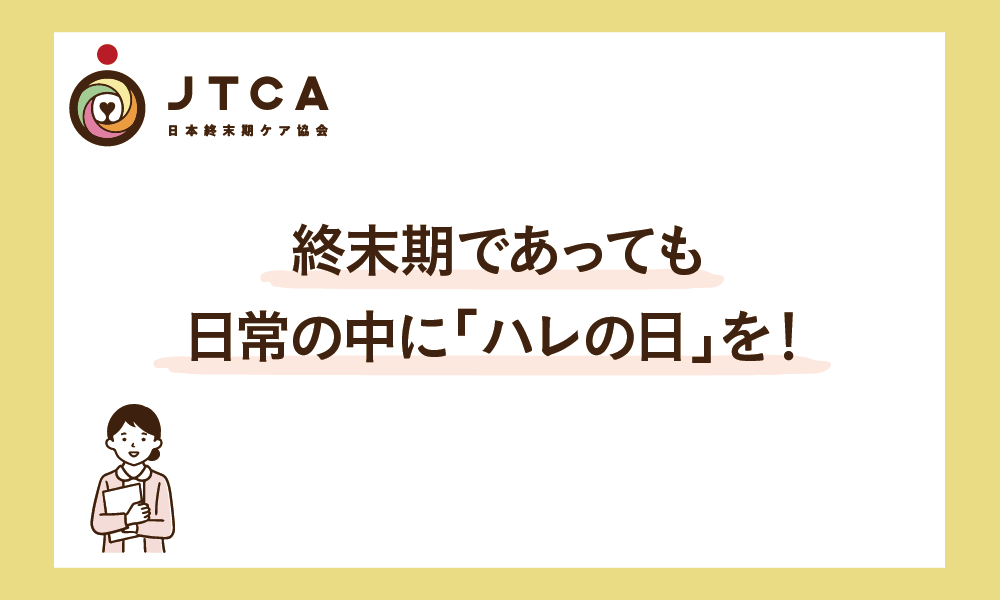
- 目次
みなさんは「ハレの日」という言葉をご存じですか?
「ハレの日」とは年中行事やお祭りなど特別な日のことを言い非日常という意味があります。
一方普段の生活である日常を「ケの日」と言います。このブログを読んでくださっているみなさんは、日々終末期にある方へのケアを実践されており、言い換えると「ケの日」である日常が穏やかに過ごせるように尽力されていることと思います。
今回日常のケアにプラスし「ハレの日」を家族と共に支援いたしましたので、みなさんへシェアさせていただこうと思います。
事例
Aさん
60歳女性
膠芽腫
積極的治療が奏効せずBSC(Best Supportive Care:がんに対する積極的治療は行わずに症状緩和の治療のみを行うこと)の方針となる。
徐々に病状が進行し、意思疎通が困難となりPS4(Performance Status4:全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす)の状態となる。
夫と2人暮らし。
夫
自営業
闘病中から熱心に付き添われており、入院中は毎日仕事終わりに病院へ面会に行っていた。Key person。
長女
実家と同市内に在住。
いろいろなことをあきらめるばかりの闘病生活
膠芽腫にて手術や放射線化学療法のため入院。入院によりいままでの生活は一変し、今までしてきたこと、これからしたかったこと等ほとんどのことをあきらめるばかりの闘病生活に、本人はもとより家族も喪失体験を繰り返してこられました。
入院から在宅療養となり数か月が経過したころ長女より、「母は『病気やから仕方ない…』と自分を言い聞かせるばかりでした。でも、一度でいいから働きづめだった母を温泉に連れて行ってあげたいんです。今の母の状態でどう思いますか?」と相談を受けました。

Aさんは意思疎通が困難でかつPS4の状態です。温泉(車で1時間程度の距離にある温泉旅館)に行くことにより「Aさんは体調変化をきたさないか?」 「実際の介護は大丈夫か?」と様々な懸念事項がでてきました。主治医やケアマネジャー、看護師とみんなで話し合いましたが、結局家族はAさんの体調を心配し温泉旅館への旅行は中止となりました。
しかし、何か一つでもお母さんに楽しい経験をしてもらいたいという長女の気持ちは痛いほど伝わりました。そこで私が勤務している医療法人社団思葉会MEIN HAUSのスタッフと話し合い、MEIN HAUSに来ていただいての日帰り旅行を長女へ提案しました。
長女と共に、
①出張シェフによるフランス料理のフルコース
②出張エステティシャンによるフェイシャルエステ
③家族も一緒に介助する入浴
④出張カメラマンによる写真撮影
を企画しました。
「ハレの日」をプロデュース!
日帰り旅行当日の参加メンバーはAさんと夫、長女、母、姉、姪。
また、MEIN HAUSの介護士と看護師、ケアマネジャー、さらに訪問看護師がそれぞれ役割分担し関わりました。
Aさんは終始穏やかな表情で過ごされており、実際には召し上がることはできませんでしたがフランス料理のフルコースを家族みんなで堪能されました。さらに、もともと美容が大好きで肌がきれいなAさんがよりフェイシャルエステで磨かれました。実のお姉さんと姪御さんがお手伝いくださりシャワー浴もしていただきました。
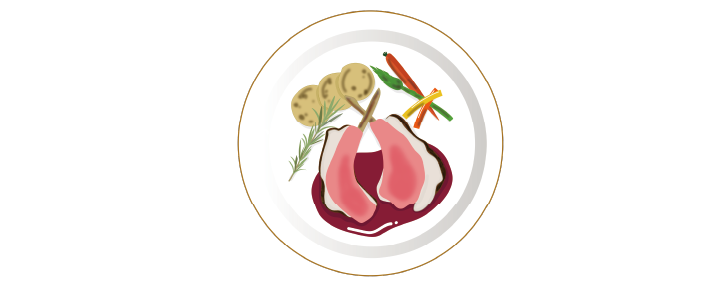
そして、この日帰り旅行の様子をプロのカメラマンが撮影してくださっていました。 日帰り旅行中のAさんの様子を見守る家族も皆さんがにこやかで、家族の満足度は非常に高く、さらにはAさんの願いを叶えてあげたいという長女の願いもかなえることができたひとときでした。
日常のケアにプラスし非日常の体験を支援する
MEIN HAUSの看護小規模多機能型居宅介護を利用されていたAさんは日々のケアは介護士や看護師により行われていました。そこへプラスして日帰り旅行という「ハレの日」。非日常の体験を支援することは、死別を意識し悩みや不安の多い終末期がん患者と家族に豊かな気持ちをもたらすと考えます。
さらに本人と家族の相互交流によって得られる肯定的な感情は家族の満足感や介護の意味づけとなり、また家族、しいては私たち支援者のエンパワメントにもつながると考えられます。
まとめ
今回MEIN HAUSでさせていただいた「ハレの日」をプロデュースするという保険請求外となる「おもてなし」ですが、みなさんはどのように感じられましたか?
そんな設備がないから難しい…、実際は忙しくてできない…と、できない理由を考えておられませんか? 「ハレの日」という非日常の体験はなにも旅行などの大掛かりなことでなくても支援できると私は思います。
コーヒーが好きな方であれば丁寧に挽いた温かいコーヒーと一緒に楽しむひと時、またいつもの食事に少し季節感を取り入れてみる(例:紅葉の季節であればもみじの葉をお皿に添える)など、非日常は色々なことで工夫し実現できると思います。
日本終末期ケア協会のスローガンである「終末期ケアはもっと自由になれる」をこれからも終末期ケア専門士のみなさんと共に体現していきたいと思います。
【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。
これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。
時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。
「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。
エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。
終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。